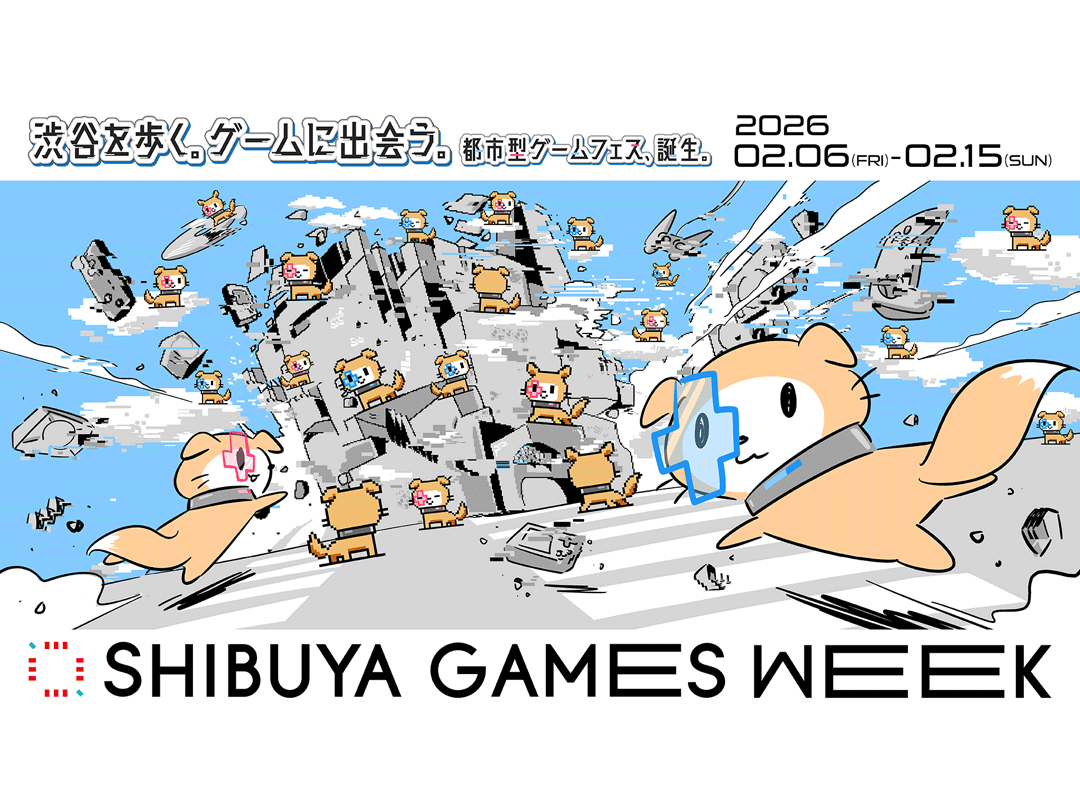SHIBUYA × INTERVIEW

メリッサ・モンジアさん(右)
Daily Tous Les Jours/デイリー・トゥ・レ・ジュール
渋谷の街に魔法をかけるアート
デイリー・トゥ・レ・ジュールが考える都市と人の関係性
2026-01-28
Daily Tous Les Jours(デイリー・トゥ・レ・ジュール)は、Mouna Andraos(ムナ・アンドラオス)と Melissa Mongiat(メリッサ・モンジア)が立ち上げた、カナダ・モントリオールに拠点を置くアート&デザインスタジオ。テクノロジーを担当するムナとナラティブを担当するメリッサが、その場所、土地にあわせ、徹底的なリサーチに基づいて創り出す作品はインタラクティブアート、ストーリーテリング、パフォーマンス、アーバンデザインを組み合わせた新分野をリードするものとして高い評価を受けている。2025年には初の著作『Strangers Need Strange Moments Together: Designing Interaction for Public Spaces』を発表し、さらなる注目を集めている。
都市の中で、見知らぬ人同士が音を奏で、つながる。カナダ・モントリオールを拠点に活動するアート&デザインスタジオ「Daily Tous Les Jours(デイリー・トゥ・レ・ジュール)」は、パブリックスペースに仕掛けを施し、人々の行動や関係性をそっと変える作品を世界各地で展開してきた。今回、渋谷で開催されるテクノロジー×アートイベント「DIG SHIBUYA 2026」への参加が決まり、渋谷の公共空間にインタラクティブ作品《Duetti(デュエッティ)》を展開する。この作品を手がかりに、DTLJのメリッサ・モンジアさんに創作の原点やテクノロジー、そして都市とアートの関係について話を聞いた。
日時:2026年1月23日(金)〜2月27日(金)
※時間帯は、国道246号横断デッキの開放時間に準じます。
場所:国道246号横断デッキ
(渋谷スクランブルスクエアと渋谷ストリームをつなぐデッキ)
主催:Daily Tous Les Jours / 東急株式会社 / 一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント
制作:株式会社シアターワークショップ
協力:ケベック州政府在日事務所 / 株式会社コトブキ
日常をキャンバスにするDTLJの誕生
最初に、デイリー・トゥ・レ・ジュールというアート&デザインスタジオについて教えてください。
デイリー・トゥ・レ・ジュール(Daily Tous Les Jours。以下、DTLJ)は私(メリッサ・モンジア)がムナ・アンドラオスとともに立ち上げたユニットです。モントリオールを拠点とし、主にパブリックスペースで人々の交流を促すアートプロジェクトの制作を手がけています。私はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでナラティブ環境デザインを、ムナはニューヨーク大学のITPでデジタルアートを学びましたが、ふたりとも「テクノロジーという魔法をかけて都市を楽しく面白い場所にする活動をしたい」と思っていました。
出会ったのは2008年です。その頃、グラフィックデザインの仕事からパブリックスペースでのインタラクティブな作品の制作に移行していた私に、友人たちが「あなたみたいに変わった人がいるのよ」とムナを紹介してくれました。知り合う前からふたりとも周りから「変わった人」と思われていたんです(笑)。
一緒にプロジェクトを手がけるうちに、ムナも私も、雨が降ろうが雪が降ろうが、屋外で人々と関わるプロジェクトが好きなんだと気づきました。バックグラウンドが違っても、ムナと私は不思議なくらいに脳がシンクロしていて、お互いの考えがよくわかります。そんな風に思える相手がいるのは本当に素敵なことだと思っています。
今はスタッフもたくさんいますが、専門性による明確な役割分担があるわけではなく、プロジェクトごとにお互いに補完し合いながら、みんなで一緒に制作しています。
英語とフランス語を混ぜたユニット名も面白いですね。
Dailyという英語とTous Les Jours というフランス語を組み合わせたもので、どちらも「毎日(日常)」という意味です。日常こそが私たちの素材であり、キャンバスであり、インスピレーションの源であり、面白く変えていきたいと考える対象です。それに、モントリオールはカナダのフランス語圏で、ムナも私も常に頭のなかで英語とフランス語の両方を使っている状態にあるので、英仏を混ぜた名前にしました。
人と人をつなぐ作品《Duetti》の思想
今回、渋谷に設置された《Duetti(デュエッティ)》はどんな作品ですか?
《Duetti》は人と人をつなぐアート作品です。イタリア語でデュエット(二重奏、二重唱)を意味するこの作品は、音を奏でるベンチとボラード(杭)の2つでできていて、それぞれの装置の中に音楽を鳴らす仕掛けがあり、そのときの動かし方やスピードによって音が変化して、唯一無二のデュエットを奏でます。スピードの速い都市を行き交う人々に、スローでリラックスできるひとときを過ごしてもらえたら、と考えて制作した作品です。
《Duetti》で遊ぶのに、わざわざ時間を取ったり、身構えたりする必要はありません。子どもに返った気分で楽しんでもらえたらと思います。知らない人同士が偶然的にベンチとボラードで音を奏で、その音がつくる音楽に耳を傾ければ、年齢や肩書き、文化的な背景を超えた思いがけない交流が生まれます。《Duetti》もそうですが、私たちのプロジェクトは、小さな仕掛けによって人と人が出会い、交流する機会をつくりだすことを目指しています。ささやかな音楽、ダンス、出会いというストーリーをきっかけにして、人々に対話を始めてもらいたいと思っています。
人との出会いやつながりの多くは、参加すること、誰かと一緒に何かをすることから生まれます。これまで何度も社会的影響調査を行ってきましたが、最近の調査結果でも、見知らぬ人との会話が生まれる割合は、同じ活動に参加することで高まることがわかっています。
DTLJは作品づくりにおいて、どんなことを大切にしていますか?
作品の制作は、コンテクストを把握することから始まりますから、まず、そこにいる人々を観察します。《Duetti》は最初、イタリア・ミラノで制作したのですが、都市の中で偶発的な人のつながりを生み出したいと考えて、直感的に音を奏でる作品にしました。音や音楽には人を惹きつけたり誘ったりする力があるからです。大切にしているのは「今ある環境は自分の行動で変えられる」ということを人々に伝えること。「《Duetti》に乗って素敵なハーモニーを一緒に奏でたら、世界がちょっと素敵に見えた」と感じてもらえたらうれしいです。
回転するベンチはどんなふうに着想したのでしょうか?
直接的なインスピレーションを与えてくれたのは、ロッキングチェアです。回転するベンチ自体を最初に設置したのは、米国インディアナ州サウスベンド市の川辺です。普段、川に目を向けていない人たちに川辺の風景をゆっくり眺めて楽しんでもらいたくて、リラックスできるベンチをつくろうと考え、ロッキングチェアに思い至りました。
ロッキングチェアの揺れるリズムに身を任せると、夢見心地になっていろんな空想が浮かんできます。だからこのベンチには《Daydreamer(白昼夢)》という名前をつけました。くるくると回るベンチなので、リラックスしながら360度の景色を楽しみ、日常を新しい眼差しで眺めることができます。誰かと一緒にこのベンチに乗ればお互いに押したり引いたりして楽しめるし、一人で乗って慣性の動きに身を委ねるとなんとも言えない浮遊感を味わえます。

手前:デイドリーマー、奥:ボラード
ユニークなメロディを奏でる装置の仕組み
技術的に特に工夫した点はありますか?
最初はアーチがなかったのですが、これでは人の目に留まらないと思ってアーチをつけました。見た目が楽しくなるだけでなく、持ち手にもなって安全性が高まりました。遊具のように立って乗ることもできますし、年配の人も安心して乗れます。特に難しかったのは、ピボット(旋回軸)の部分でした。回転速度が速すぎると、子どもが落ちてケガすることもあり得えます。そこで、ゆっくりと回るピボットを開発するため、さまざまなイノベーションを盛り込んで、磁気ブレーキをつかった複雑なシステムを開発しました。
また、足下のディスク(円盤状の台)は、乗ったときに出る音が素敵な音楽を奏でるようにしてあります。ディスクは4つの部分に分かれていて、4つの部分それぞれに違う音が設定されています。各部分の境目には突起があり、突起を超えてベンチを回すにはちょっと力を入れないといけない仕掛けになっています。ぐるっと一周すると多くの声が重なるアルペジオが流れ、足下のディスクから出る音に重なると、さらに複雑なメロディが生まれて、ベンチに乗りながら作曲しているような気分になります。
ボラードは、街中で見かける杭(ボラード)を参照しました。ボラードは通常、車や人が進入していい場所とそうでない場所を区別するために設置されるものですが、《Duetti》のボラードは周りで遊んだり歩いたりするためのものです。ディスクの上を思い思いの方向に歩くと和音が響き、ピアノの弾き方や作曲のしかたをまったく知らない人でも短い曲がつくれてしまいます。装置にはいろいろな和音が設定されているのですが、どんな風に歩いても、調和の取れたハーモニーを奏でるようにできています。
乗ってみると、まるでコーラスのような不思議な音がします。
音楽的なインスピレーションの1つは聖歌隊の合唱でした。イタリアっぽいと感じるかもしれません。どこかフェリーニっぽくもありますし、バロック音楽の合唱のような響きもあります。身体を動かすことはさまざまな脳神経学的作用をもたらすことが科学的にわかっています。歴史的に治療と拷問の両方に使われてきたくらい、人の精神に強く働きかける力があります。
また、音楽に乗って身体を動かすという本能的な行動も、心身によい影響を与えることがわかっています。他の人と一緒に演奏したり歌ったりすると、大量の幸せホルモンの分泌が促されます。音を奏でるベンチに乗って身体を揺らすと、目を開けたまま楽しい夢を見ているような気分になり、ストレスから開放されて、想像力が湧いてきます。また、動きが生む音を耳にすると、もっと身体を揺らしたくなるはずです。
《Duetti》に乗ると、誰もが自然と笑顔になる
渋谷で「ラララ」と歌いたくなる瞬間をつくる
渋谷の街でパブリックアートを展開するにあたって、特に気をつけたことはありますか?
新たな場所でプロジェクトを手がけるときには、新しいコンテクストと向き合うことになります。今回、渋谷で制作できることをとてもうれしく思っています。というのも、東京を想像するとき、誰もがイメージする街が渋谷だからです。渋谷は常に大量の人が行き交う街ですが、スマホを見ながら歩いている人、急いでいる人も多いので、作品に目を留めてもらうのは簡単ではありません。
《Duetti》の設置場所は、国道246横断デッキ(旧東急東横線ホーム)です。中庭のような広がりのある空間ですが、少し奥まった場所でもあるので、いろんな人に気づいてもらえるように、かつて東横線渋谷駅のシンボルだった「カマボコ屋根」の下のパネルにキャッチコピーを看板にして掲げています。目的地に向かって忙しく行き来する人たちがふと目を留め、《Duetti》に乗って、つかの間でもストレスから解放されて楽しんでくれたらうれしいです。
また、JR渋谷駅に隣接しているので、駅のホームや電車の窓からも看板や作品が垣間見えます。デッキを行き交う人だけでなく、駅にいる人や電車の中にいる人の目にちょっとしたショーのように見えたらいいですね。「何か面白そうなことが起こっているのかも?」と気づいてもらえたらうれしいです。
「私たちは毎日『ラララ』する」などキャッチコピーも楽しいですね。
「ラララ」の部分は《Duetti》の音楽的な体験にも通じています。「ラララ」は年齢も言語も関係なく、ご機嫌なときに思わず出る世界共通のフレーズです。例えば子どもは気分がいいとき、思わず「ラララ」と歌い出しますよね。4つ掲げたキャッチコピーのうち「知らない人同士、ふしぎな瞬間を共有してみよう」は、私たちの著書のタイトルであり、活動のモットーです。通りすがりの人が、偶然一緒に《Duetti》に乗って時間を共有し、ささやかな縁を結ぶ——そんなふうにして今という時間を楽しんでもらいたいと思っています。
DTLJは世界各地でパブリックアートを手がけていますが、今回、渋谷で展示を行うにあたり、渋谷という街にどんな印象をもちましたか?
以前、東京に来たとき、渋谷近辺に滞在したのですが、賑やかな大都会でありながら、裏通りに入ると静かに過ごせる場所が見つかるし、不思議なことにどの道も結局渋谷駅に通じていて、方向感覚がつかめないのも面白かったです。世界のどこにもない、本当に唯一無二の街だと思います。ツーリストにとっては、スクランブル交差点のとてつもない人波や、その中に身を置くこと自体が驚くような体験ですし、他の場所では得られないユニークな感覚をもたらします。モントリオールも観光都市でツーリストが多いと感じることはありますが、渋谷の雑踏の圧倒的な規模とは比べものになりません。

渋谷という都市にはどんな可能性があると思いますか?
渋谷はスピード感があって光り輝く場所、いろんな文化が生まれる大都会です。スクランブル交差点のように、都市の中に誰でもアクセスできる賑やかでオープンな空間があることは、都市にとって大きな意味があります。そうした空間で行われる活動を通じて人々は自分の街にプライドをもちますし、自分の街の一部だという帰属感が生まれます。そうした感覚は、自分の生き方、自分にとって大切なものは何かという大切な問いに向き合うことにもつながります。渋谷にはそんな場所がたくさんあると思います。
DTLJは、世の中の人みんなに文化へのアクセスを提供することを大切な目標の1つにしています。作品をミュージアムで展示することもありますが、ほとんどはパブリックスペースに設置しているのもそのためです。今回の渋谷の会場は、屋外の公共空間でありながら屋根があるので、ゆっくり楽しんでもらえる場所になったと思います。


渋谷での展示の様子
渋谷で、いつかこんな作品をつくってみたい、と思ったりしましたか?
いつか渋谷に満ちているパワーを生かしてたくさんの歩行者が参加するコレオグラフィー作品を作ってみたいなと思いました。初めて渋谷の街を目にしたのは、Netflixの配信ドラマ「今際の国のアリス」の冒頭に登場する静止状態になった渋谷スクランブル交差点です。宇宙の中での自分という存在の小ささを感じる場面を見て、ここでコレオグラフィー作品、つまり人々がダンスする作品をつくったら面白いだろうなと思ったのです。もちろん、実現するには、気をつけなければならないことが山のようにあると思いますが。
私たちは、ダンスを取り入れた作品もこれまでたくさん制作してきました。ダンスもDTLJの制作活動の重要な要素の1つです。歩き方、身体の動かし方、踊り方によって、心身にさまざまなよい影響があることがわかっています。特に、みんなで一緒に踊ると「自分は大きな集まりの一部なんだ」という一体感、連帯感が生まれる点は重要です。社会性動物である人間の基本的欲求に直結する感覚だからです。
分断の時代、アートを「つなぐ力」に
DIG SHIBUYA 2026は渋谷を舞台としたテクノロジー×アートのイベントですが、DTLJもアートのもつ詩的な要素とテクノロジーを組み合わせた作品を手がけています。DTLJにとってテクノロジーとはどんな存在ですか?
ムナはDTLJを始める前から、人々のテクノロジーへのアクセスを広げる活動を手がけていました。それが今のDTLJの「人々にテクノロジーを含む文化へのアクセスを提供する」という活動につながっています。しかし、制作やリサーチを続けるうちに、本来人と人とをつなぐはずのテクノロジーが、今や私たちがつながることを阻んでいる面があるという現実にも気づきました。
今、テクノロジーは非常に巧妙な形で私たちを分断しています。誰とつながり、どこに行き、誰と出会うかという選択を知らないうちにアプリが決めているし、アルゴリズムが似た人ばかりが集まるエコーチェンバーに人々を閉じ込めています。その結果、格差や社会の分極化が進み、世界中に孤独が蔓延して、至るところで大きな問題になっています。まさに孤独のパンデミックです。
そうした状況をふまえ、私たちは作品制作において、人々をつなぐためにテクノロジーを活用しています。
一方で、DTLJにとってアートとはどんな存在なのでしょうか? 特にパブリックアートの制作を数多く手がける理由を教えてください。
デザインを学んだ私にとって、パブリックアートとは、外の世界を自由に探究し、有意義なイノベーションを起こすための手がかりです。おそらく渋谷もそうだと思いますが、都市は均質で無機質な空間になりがちです。そんな都市にもう一度魔法をかけて面白くしたくて、パブリックアートを制作しています。群衆の中にいると、私たちは自分を見失いがちです。自分を閉ざし、行き交う人、すれ違う人を気に留めず、無関心になるのが当たり前になります。そんな都市空間で、人々が自分らしさを取り戻し、人とのつながりを感じられる場所をつくるには、アートの力が必要です。
人間は社会的動物であり、たとえ内向的な人であっても、知らない人と話をしたり、ちょっとした手助けをすることで、脳内に幸せホルモンが分泌されることがわかっています。パブリックアートに触れて「ここは自分たちの場所だ」という感覚をもつと、人はまた出会いを求めてここに足を運びたくなります。たしかに、スマホや美術館でも、一人または少人数でアートを「見る」ことはできますが、たくさんの人が一緒にアートにアクセスしているという感覚にはなりにくいものです。
しかし、参加型パブリックスペースのアートの場合は、参加する人も作品の一部になり、見ているだけのときとは違う、場所に魔法をかけるような面白さが生まれます。《Duetti》もそうで、装置だけでなく、乗って動く人の動きやそこから生まれる音やその場の雰囲気も作品の一部になります。人と人が一緒に何ができるだろうかと考えることには希望があるし、可能性があります。アートとは、希望であり、可能性であり、自由なのだと思います。
制作においては、人と人との交流を生み出すナラティブやストーリーも大切にしているとうかがいました。
私自身、大学院ではナラティブ環境を専攻しましたし、ストーリーやナラティブには人を結びつける力があると実感しています。ストーリーは、人の心を魅了し、普段の行動を変えて新しいことを試してみようという気持ちをかき立てます。「人生をどう生きるのか?」「今はどんなことができていて、これからどんなことができる可能性があるのか?」「それを実現するにはどうしたらいいのか?」——ストーリーはそうした大切な問いを一人ではなくみんなで考え、実現していくための手がかりになります。
ストーリーを生み出す方法について、私たちはさまざまなジャンルのアートや文化を参考にしています。ダンス、とくにみんなで踊ることも、私たちの制作における大切な要素です。舞踊家のピナ・バウシュの作品からは、たくさんのインスピレーションを受け取りました。最近では、エネルギッシュで元気が出るK-Popのダンスを参考にすることもあります。
映画を参考にすることもあります。例えば、タル・ベーラ監督の映画「ヴェルクマイスター・ハーモニー」のバーにいる人々の場面から着想して作品をつくったこともあります(《人と太陽系のためのコレオグラフィー》)。音楽も重要で、私たちはよく作品に音楽を使いますし、作品ごとにさまざまなミュージシャンとコラボレーションしてきました。音楽は言語を超えて人々をつなぎます。年齢を問わず、音楽を聴くと私たちの身体は反応するようにできているんですね。例えば、初期に制作した音楽を奏でるブランコ《Musical Swing》は好評を得て、その後もシリーズとして各地に展開しています。
そして何より、ミュージシャンも含め、プロジェクトを通じて出会ったさまざまな人からたくさんの刺激と力をもらいました。人との出会いがその後のプロジェクトにつながって今に至っています。
音楽を奏でるブランコ《Musical Swing》
最も身近な人のつながりでいえば、メリッサさんもムナさんも数年前にお子さんが生まれましたね。母となったことが作品制作に影響している部分はありますか?
ベータ版のテストをしてくれる人が増えましたね(笑)。子どもがテストに参加して遊んでくれるので、発想が広がったと感じています。また、母親業に加えて老いた親の介護も始まっていて、睡眠時間は減ってしまったのですが、異なる世代間の関係や影響、相互作用の重要性に今まで以上に目を向けるようになりました。
何より、子育てをしていると、世界に対する希望や可能性があふれてきます。子どもに残していくことになる世界をもっとよいものにしていかなくては、という責任感も改めて感じています。

「子育てを通して、世界への希望と責任を感じている」というDTLJのふたり
取材・文/川上純子 写真(渋谷のDuettiのみ)/Yasuko Tadokoro